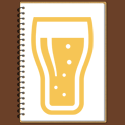クラフトビールを嗜み始めると、これまで聞いたことのない言葉にたくさん出会います。クラフトビールの謎のワードを覚えるためのノート
メニューによく書いてある言葉
Alcohol By Volume=ABV アルコール度数のこと。日本の酒税法では摂氏15度のときに原容量100分中に含まれるエチルアルコールの容量。「%」も「度」も同じ意味。
International Bitterness Units (国際苦味単位)。ビールがどのくらい苦いのかを示す単位。ホップをどのくらい使ったのか、どのくらい煮込んだのか、α酸(ホップの花に含まれているホップの苦味の源)の含有量の多いホップを使ったのかどうか、…という作る過程の条件から求められるあくまで計算上の数値。
IBU0とされるビールもちゃんと苦かったし、IBU500とされるビールも苦くて飲めないなんてこともなく、意外と普通の苦さだねってなったことがあります。
Standard Reference Method(標準参照法)。ビールの色を度数で表す。「米国醸造化学者学会」が採用していて、日本でもSRMで表されることが多い。ヨーロッパでは「ヨーロッパ醸造協議会」による規格、EBC (European Brewery Convention)が使われる。
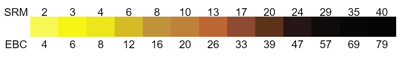
ここで詳しく説明されてます
ビールの容量の単位。イギリスのUKパイント(568ml)、アメリカのUSパイント(437ml)がある。日本のビアバーでは、大抵一番大きいサイズのグラスがコレにあたる。(まれにMass(マース)と呼ばれる1リットルのジョッキがあることもある)
飲み比べのセットのこと。ミニグラスで3種類くらいをテイスティングできるセットにしていることが多い。3種類の合計で1パイント分くらいが飲める。いろんな種類を試したいときには迷わずコレをオーダー!
ビールの説明によく出てくる言葉
アロマとフレーバーどっちも「香り」を表す言葉。
アロマ=鼻で感じる香り
フレーバー=口に含んだ時に感じる香り
キレ=後味がどれだけ尾を引くか
後味がスッと消えるようであれば『キレがある』と言える状態。
コク=いろんな味がするか
5味と呼ばれる甘味、旨味、苦味、塩味、酸味がバランスよく感じられるのが『コクがある』という状態。
ビールの評価基準のひとつで、飲みやすさのこと。何杯も飲みたくなるビールかどうか、という評価基準。「また飲みたい、もっと飲みたい、飲み続けられる!」という感覚がもてるビールがドリンカビリティが高いといえる。
ビールの原料
読んで字のごとく「発芽した麦」。モルト(malt)とも呼ばれる。ビールに使われるのは二条大麦。水に浸して発芽させ、乾燥させ、芽と根を取り除き、さらに焙煎する。
なぜわざわざ発芽させるの?
発酵させるのに「糖」が必要だが、穀類である大麦そのものには糖がない。発芽させることでアミラーゼが活性化し、それをお湯で煮込むとアミラーゼが大麦のでんぷんを糖に分解してくれるため。
ここで詳しく解説されています
アサ科のツル性多年草。ツルの高さは7から12メートルになる。雌雄異株。和名はセイヨウカラハナソウ(西洋唐花草)。ビールの原料となるのは「毬花」と呼ばれる雌花に出来る松かさに似た花のようなもの(厳密には花ではない)で、毬花にあるルプリンと呼ばれる黄色の粒子が苦味、香りに作用する。
ここで詳しく解説されています

糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物のこと。
ビールに使われる酵母は「上面発酵酵母(エール酵母)」「下面発酵酵母(ラガー酵母)」「天然酵母」と大きく分けて3種類。
ここで詳しく解説されています
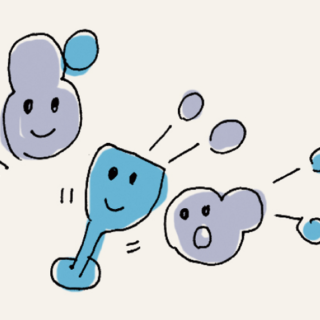
お店でよく聞く言葉
ビールをグラスやジョッキに注ぐための器具。ビールの入っている樽などの容器に炭酸ガスを送り込み、その圧力で中のビールを押し出す。
ビールの注ぎ口のこと。10タップ=10種類の樽生ビールが飲める
お店の全てのタップを、特定のブルワリーのビールで埋め尽くす事。テイクオーバーとは乗っ取るという意味。